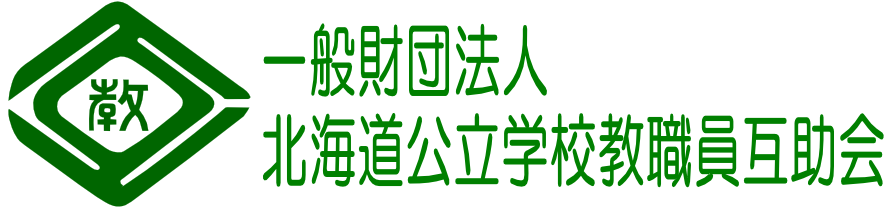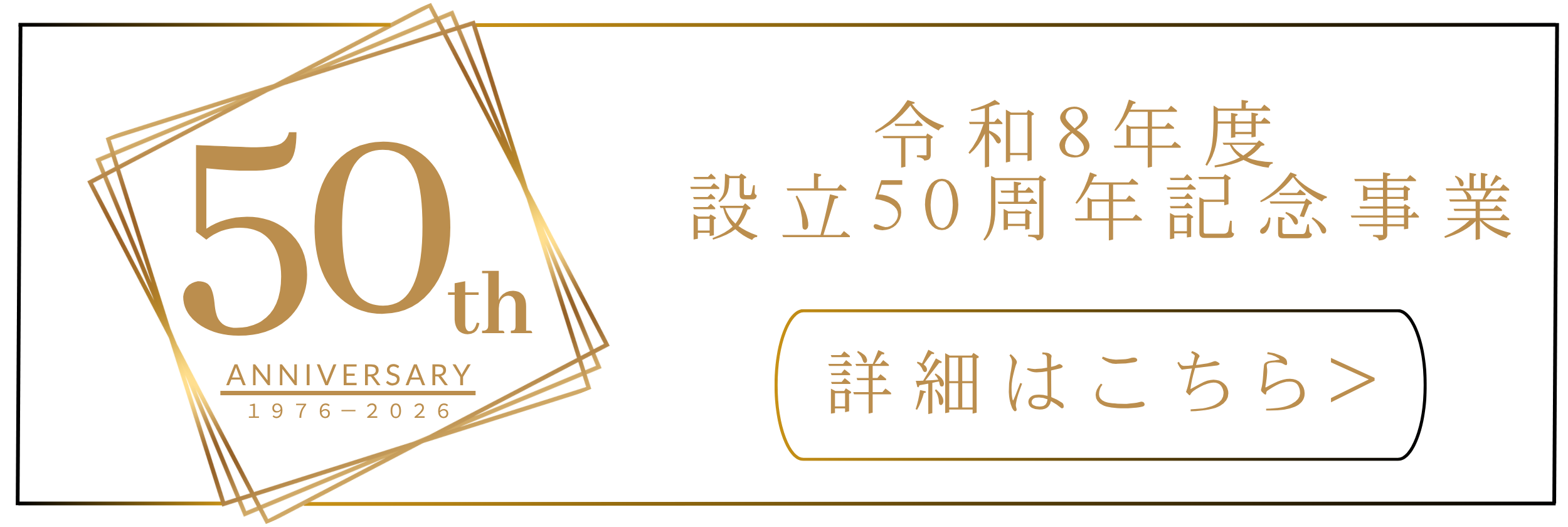後期高齢者医療制度の実施に伴う互助会の取扱いについて(現職会員の扶養親族関係)
公立学校共済組合及びそれ以外の健康保険組合において、現職会員の被扶養者として認定されている方のうち、75歳以上の方(65歳以上の一定の障がいのある方で、加入を希望する方を含みます。)は、平成20年4月1日以降、公立学校共済組合等の被扶養者としての資格を失い、後期高齢者医療制度に加入しています。
このことにより、公立学校共済組合等の被扶養者はもとより、互助会現職会員の被扶養者からも外れることとなり、給付等を受けることができなくなります。
このようなことから、互助会では、会員に対する給与上の扶養手当支給の基礎となっている後期高齢者医療制度の加入者(以下「後期高齢者扶養親族」といいます。)について、新たに給付等の対象者として認定することにより、引き続き給付等を行うこととしていますので、後期高齢者扶養親族に該当する方を扶養されている会員の方は、次を参考に手続きを行ってください。
■届け出に必要な書類
■届け出(認定・取消申告)の必要な方
■認定申告
・会員の扶養手当支給の基礎となっている扶養親族の方が、新たに後期高齢者扶養親族に該当することとなった場合(75歳の誕生日を迎え、後期高齢者医療制度に加入した場合)
・後期高齢者医療制度に加入している方が、新たに会員の扶養手当支給の基礎となる扶養親族に認定された場合
■取消申告
・後期高齢者扶養親族に係る会員の扶養手当が取り消された場合
■届け出(認定・取消申告)の必要な方
・新たに後期高齢者扶養親族に該当することとなった場合、後期高齢者医療制度の加入日をもって、後期高齢者扶養親族として認定します。
・後期高齢者医療制度の加入者が、新たに会員の扶養手当支給の基礎となる扶養親族として認定された場合、当該扶養手当認定の日をもって、後期高齢者扶養親族として認定します。
・後期高齢者扶養親族に係る会員の扶養手当が取り消された場合、当該扶養手当の取消年月日をもって、後期高齢者扶養親族の資格を喪失します。
■対象となる給付金
・入院見舞金
・へき地医療交通費補助金
・弔慰金
・介護給付金
・指定宿泊施設利用補助金
後期高齢者医療制度の実施に伴う互助会の取扱いについてのお問い合わせ
◇担当 給付貸付グループ
◇電話番号 011-211-6073(給付貸付グループ直通)